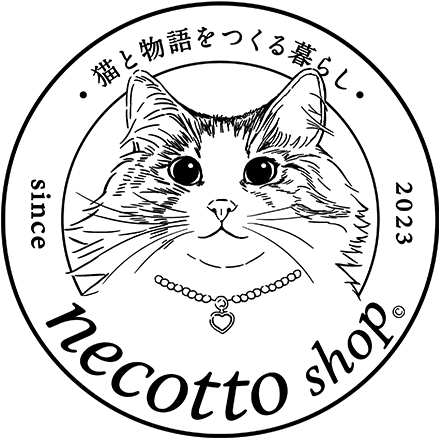陶芸家 2023.07.14 陶芸家と〝みゃ~んちゃん〟



群馬県安中市下秋間…人里から少し離れた緑豊かな山あいに 陶芸家 青木昇さんの営む“自性寺焼里秋窯(じしょうじやきりしゅうがま)”があります。春には、広大な秋間梅林に咲く満開の梅花と、一面に漂う芳しい梅香に誘われ、多くの人で賑わいを見せます。群馬県は紀州に次いでそのシェアを誇る梅の生産地でもあります。

『自性寺焼由来』
そんな安中市の秋間地域は、焼き物のふるさととしてその昔「飽馬(あくま)の里」と呼ばれていました。中山道安中宿の北方に位置し、碓氷峠へと連なる、なだらかな丘陵地で、山あいを縫う清流と良質な粘土、豊かな赤松の樹林など、四季の織り成す自然に恵まれた沃地として歴史を重ねてきました。
奈良時代から平安時代にかけて、関東地方最大級の須恵器の産地として、各地に出荷され続けてきました。こうした伝統の元、江戸時代中期(天明3年以前)より、自性寺の地に窯が築かれ、おびただしい数の焼き物が生産され、自性寺焼の最盛期として開花しました。
『自性寺焼の特徴』
主に生活用器のほか芸術味豊かな作品も多く、温かみのある風合いを備えた焼締陶器から釉薬陶器、また一部には色絵陶器まで焼かれ、今もなお古民芸陶器として珍重されています。
しかしながら・・時代の流れには逆らえず、この自性寺焼は日露戦争直後の明治38年(1905年)に、最後に残っていた窯元が益子へ移り、その長い伝統の火は惜しくも消え去ってしまうこととなりました。
『焼き物との出逢い〜自分の手しか信じるものがない〜』
工業高校で染めと化学を専攻した青木さんは、卒業後に京都で染めものの職に就いたものの、程なく体調を崩し帰郷することになりました。木の温もりが好きだった青木さんは、手づくり家具の仕事へと導かれて行きますが、時は高度経済成長期とあって、家具づくりは工業量産の時代へと移行。ものづくりを目指した青木さんは、夢とは程遠い現実に直面し途方に暮れてしまいます。
そんな時に友人から貰った益子焼きに、「これだ!」と心を躍らせました。まさに青木さんと陶芸との出逢いでした。
『独学から独自性へ、無から有を生み出す喜び』
人に頭を下げて教えてもらうことが苦手な青木さんは、陶芸を独学で学びました。本を読み、粘土を買い、自ら窯を作り、焼いてみる。分からないことは産地に出向き、つぶさに職人さんの仕事を見て、そこで交わされる会話を聞くことで大抵は解決できました。自身で考えながら試してみる…を繰り返し、無我夢中で作陶の腕を磨き上げていきました。
何より楽しいと思えたのは、形のないものから形を生み出すこと。柔らかな土から硬いものができる神秘性は不思議だけれど、楽しくもあります。1,200℃を超える熱で7昼夜もの時間をかけて焼き上げたその出来映えをジャッジする自らの目と感性だけが励みでした。これもダメ!まだダメ!と決して甘えることなく、焼き上がった作品を一つ一つ厳しく見定めていく日々の積み上げは、青木さんの技術を高みへと引き上げます。
師匠がいないから…などと絶対に言わせるものか!焼き物への強い信念は、当時 伊香保に隣接する水沢の工房にいた青木さんを、忘れ去られようとしていた自性寺焼と引き合わせることとなります。 それまで、買った粘土を使っていた青木さんを引き寄せたのは、安中市の焼き物の歴史とその土地を覆う地面に眠る粘土の存在でした。
この貴重な焼き物文化と大地の豊かな恵みを再見し、古窯跡の調査研究と無尽の陶片に、極めて高品質な陶土が埋没されていると確信した青木さんは、昭和53年(1978年)、実に73年ぶりに自性寺焼を復興するに至ったのです。一貫して地元産の陶土に拘り、作陶に専念し続け、自ら登り窯や穴窯を築き、往時を凌ぐ温もりを備えて生み出されたこの焼き物こそが今日の青木流の誕生です。
『美しき陶器・・金花紋(きんかもん)と紫陽花釉』
まるで金色の蕾が、無数の花を咲かせる瞬間のような美しい紋様の器と、コーヒーを淹れて出して頂いた紫陽花色のマグカップは、いずれも釉薬(うわぐすり)を使った青木さんならではの独創的な器です。ずっしりとした重みと厚みでありながら、持つ手にも、触れる唇にも優しく馴染む表層の滑らかさは、高品質と云われる自性寺の土の質感そのものなのかも知れません。煌びやかさと、溢れんばかりに漂う気品を備え、際立った美しさを放つ金花紋の器は、それを手にする人の心をどれほど豊かにすることでしょう。これこそが青木さんの心底の想いであり、陶器を生み出す歓びであることを感じずにはいられません。
様々な条件が絶妙なタイミングで合わさってこれらの色と紋様が浮かび上がります。まさにサイエンス!同じものは二つとできない逸品です。



『大嫌いだった土の温かさと愛おしさ』
子どもの頃は、勉強より畑仕事を手伝うことが当たり前の時代に育った青木さん。トラクターやコンバインなどもなく、牛で田畑を耕し、田植えも全て手作業…。嫌になるくらい触れた土が、今は愛おしい陶器となって自らを喜ばせてくれている因果を、不思議なものだとしみじみ語ります。
とてつもなく永い年月を超えて地層を重ね、大地を覆う土は、計り知れないエネルギーを蓄えています。自性寺焼で青木さんが使用する土は、日本列島がまだ形成されていない、「新生代第三紀層」という、大陸と地続きだったおよそ1,000万年を遡った地層のものだと云います。


土とは地球、いや宇宙そのものなのかも知れない・・。陶芸とはロマンそのものなのです。 青木さんが本当の意味で、大自然の中から美しい「有」を生み出すことができるのは、幼少時からその手に触れた大地の温もりをご存知だったからと云えましょう。
『出会いは突然に・・』

ミャ~ン、ミャ~ン… あぁ、猫か。ひと気のない場所だ、きっと捨てられたのだろう‥ 微かに聞こえたその小さな鳴き声はいつまでも止むことなく続く。それは2017年5月末の小雨の夜のこと。お腹を空かせて親を探しているのか、あまりにか細い鳴き声が切なくて可哀そうで、私は心を締め付けられました。
外へ出てみると、揚々と茂り始めた緑の草葉の間から真っ白な子猫が、透き通るような青い目でこちらを見つめている。真っ暗闇なはずなのに、まるでそこだけ月の光でも当たっているかのように浮かび上がるその顔のなんと可愛らしいこと!しかし、警戒心が人一倍強く、寄り付くことはありません。それでもミャ~ンミャ~ンと鳴き続ける子猫の姿に、どうしたものかと困り果ててしまいましたが、この時、この仔はすでに私の心に住み着いてしまったのかも知れません。

猫なんて飼ったこともなかったので、どうしたら良いか分からなかった。とりあえずドッグフードを毎日少しずつ与えながら、ちょっと頭に触れてみた。食べる時しか近寄って来なかった彼が、数日後、スッと工房に入ってくれたのです。
あの夜の鳴き声をとって『ミヤ~ン』と名付けました。よく懐いてくれました。本当に美しい猫だ。ネットで調べてみると、その風貌から、どうやらトルコのヴァン猫に似ていることが分かりました。白い毛と青い瞳、長い手足としっぽ。気高く、警戒心が強い。飼い主にしか懐かない・・というその性質までも似通っています。はてさて、お前はどこからやってきたの?
『甘えん坊の赤ちゃんのまま‥』

生まれて間もなかったミヤ~ンは、よほど母猫が恋しかったのか、私のお腹に吸いついて甘えるようになりました。5歳の今でもそれは変わりません。ウチには子どもがいませんから、子どもを育てるような気持ちを味わわせてくれます。 感じたことのない愛おしさに、出先で帰りが遅くなろうと泊まらないで絶対に帰るようになり、私を待っているその健気な姿を見ては、さらに可愛さが増す・・という日々。ミヤ~ンが体調を崩した時には、医者に行く度に具合の悪くなる姿に居た堪れず、その医療措置を最小限にとどめ、日常生活の改善を中心に彼に寄り添い、症状を和らげてきました。
仕事の時も食事の時も、寝る時も・・片時も離れることのないミヤ~ン。彼と暮らすようになって、私自身本当に穏やかになりました。
……………
これから先は本当に好きなものを気の向くままに作ってみたい。 70歳を過ぎ、思いがけず生活を共にすることになった初めての猫の存在は、それまで余りに忙しすぎた青木さんの心に新しい感性を確実に宿してくれているように感じます。その日々の暮らしは、自性寺の大地と作品の中にしっかりと刻み込まれていくはずです。
家族以外にはなかなか心を開かないミヤ~ンちゃんですが、取材内容は彼と大好きな青木さんのこと。どうやら気を良くしてくれたようで、この日はとても好意的に、その気高くて美しい姿を横たえてポーズを取り、「ミヤ~ン」という甘い美声を惜しみなく聞かせてくれました。


取材・執筆:吉村巳之/写真:吉村巳之

青木昇(あおきのぼる)
自性寺焼 里秋窯
群馬県安中市下秋間4670-1
URL=https://jishojiyaki.jp
現代の名工(卓越技能章)、黄綬褒章受章
群馬県指定ふるさと伝統工芸品
安中市指定重要無形文化財保持者(群馬県の陶芸家で唯一)

吉村巳之
ヘア & メイクアップ、着付け、ウェディング、撮影/ステージ用ヘアメイク、企業/各種コミュニティ向けイメージアップ講座、ホリスティックビューティー講座、たかさき能/狂言を観る会実行委員会、子宮頸がん予防啓発高崎美スタイルマラソン実行委員会など各分野で活動中