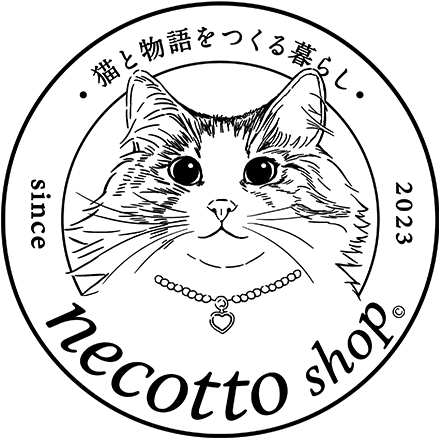創作 2023.09.07 吾輩は野良である

吾輩は野良である。
名前は……ないこともない。
もちろん、私としてはどれひとつとして認めてはいないのだが、人間たちが好き勝手に呼ぶのだ。
「みーちゃん」「トラちゃん」「にゃんちゃん」「ちびちゃん」
私はそんな名ではないぞ、と鳴いて抗議するものの、人間たちはそれを返事と見なすらしい。
なんとも人間とのコミュニケーションとやらは厄介である。
さて、私の1日は早朝から始まる。
朝早くから散歩をしながらパトロールをし、ついでに朝食を済ませる。
私の縄張りにはどうも猫に好意的な人間が多いらしい。
私の通り道には「どうぞお食べください」と言わんばかりに、食べ物が用意されているのだ。
同胞たちも集まってくるため、ときには取り合いになることもあるが、私がいつも仲裁している。
朝食を済ませると、適当なところで昼寝をする。
日当たりのいいところで寝転がっていると人間が邪魔をしてくることもあるが、人間が入ってこれない場所を私は知っている。
無論、それをここで明かすつもりはない。
じっくりと昼寝をした後で、また散歩をしながらパトロールをする。
人間がかまってほしそうにしていると、気が向いたときだけゴロンと横になって撫でさせてやる。

人間は知らぬかもしれないが、撫で方にも上手い下手がある。
撫で方が上手い人間とは長めに戯れてやるのが私の主義だ。
ひとり、私のことを「ちびちゃん」と呼ぶ人間がいるのだが、この人間の撫で方は実に素晴らしい。
スーツを着ている女性でいつも決まった時間に私を探しにやってくるので、最近では私が彼女を待っていてやるのだ。
その後はまた昼寝をして、小腹が空いたら顔馴染みの家や店に出向く。
夕食は食べたり、食べなかったりする。
人間が夕食を用意している場合にはそれを食べるが、常に用意されているわけではない。
狩りをすることもあるが、それが失敗することもある。
そして、空腹であるか、満腹であるかに関係なく、夜になると集会に向かう。
すぐ近くに空き地があり、そこが集会所になっているのだ。
「川の近くで見ない顔の奴に出くわした」
「あそこの家主は猫嫌いらしい。ちょっと挨拶しただけでえらい目に遭った」
「近頃はやたらとカラスの奴らが絡んでくる」
「あの角に新しく引っ越してきた人間は気前がいいらしい」
お互いに情報交換をして、集会を終える。
この猫の集会についてはなぜか人間も知っているらしく、私たちが情報交換している姿をわざわざ見に来る人間もいる。
いつだったか、同胞の1匹が「こいつがずっとついてくるんだ」と人間を連れて来てしまったこともあった。
同胞たちがじっとその人間を見ていると、気まずくなったのか人間は「すみませんでした……」と逃げて行った。
集会が終わると寝床に戻り、そこで私の1日は終わる。
代り映えのない毎日だ。
ただ、平穏だった日々を「代り映えのない毎日だ」などと言ったバチが当たったのか、
その翌日、怪我をしてしまった。
今考えてもなぜそうなってしまったのか、自分でも本当にわからない。
普段から道路には絶対に出ないようにしていたのだが、そのとき、道路の向こうに綺麗な蝶が飛んでいるのが見えたのだ。
一度はぐっと堪えた。
でも、その蝶から目を離すことができず、その不規則な揺らめきに私は思わず駆け出していた。
気付いたときには横たわっていて、体が動かなくなっていた。
「可哀想……」
「ああ、ここ車多いから……」
人間の声がチラホラと聞こえる。
ああ、私の命はこんなところで終わってしまうのか。
まぁ、でも野良としては十分に生きたのかもしれない。
私は野良の母のもとに生まれ、野良として育った。
幼い頃は他の兄弟たちもいて、それなりに騒がしい毎日だった。
それでも気付けば兄弟が1匹減り、また1匹減り……最後に残ったのが私だったのだ。
母1匹、子1匹の暮らし。
だが、その母もある日、突然帰ってこなくなった。
当時は母が私を置いてどこかに行ってしまったのだと泣き続けたが、ここまで生きてみてよくわかった。
きっと母も今の私と同じだったのだろう。
母がいなくなって、それでもどうにか1匹で生きていけるようにと必死で足掻いてきた。
今の縄張りを持ってからは、新参者に「ボス!」と呼ばれるまでになった。
喧嘩では負けなくなったし、カラスの奴らだって追い払える。
人間の扱いだってお手の物だ。
ああ、雨まで降ってきた。
どんどん体が冷たくなっていく。
今までのことが走馬灯のように駆け巡る。
共に生きた同胞たち、世話になった人間たち……。
ああ、最後にあのスーツを着た女性に撫でられたかったものだ。
薄れゆく意識の中で、「ちびちゃん!」という声が聞こえた気がした。
しばらくすると、視界がぼんやりと明るくなってきた。
それにもう寒くない。
ああ、天国というのはこういうところなのかと思っていたが、カチャンという金属音や不思議な臭いでここが天国ではないことに気付かされた。
知っているぞ……ここは確か病院。
白衣を着た人間が額に汗をにじませながら私の体に何かをしている。
あのスーツ姿の彼女も心配そうな顔で私を見ている。
ああ、やめろ……私の体を好き勝手するな……。
そう思いながらまた意識を手放した。
次に目覚めると痛みは残っていたものの、体が動くようになっていた。
「ああ、よかった。思ったよりも元気そうですね。もう大丈夫ですよ、かなこさん」
「よかった……ちびちゃん、本当によかった……」
なるほど、彼女は「かなこ」という名らしい。
かなこは相変わらず私のことを「ちびちゃん」と呼んでいる。
いつものように違うと言ってやろうかと思ったが、私を見てポロポロと大粒の涙を流しているかなこを見ると面食らってしまった。
それから私はかなこの家に連れていかれた。
最初のほうこそ「私は私の縄張りに帰るのだ!」と抗議をしていたが、私のツボを的確に押さえた絶妙な撫で方に、食と住まいが完備されたこの空間が心地よくなってしまった。ここには天敵もいない。
あの憎き車とやらもいない。
縄張り争いをすることもなければ、食べ物の心配をすることもない。
不満と言えば、時々かなこが私を病院に連れていくこと。
どうにもあの雰囲気と臭いは苦手である。
窓から外を眺めていると外が恋しくなることもあるが、快適な空間で腹を見せながらゴロンゴロンと寝転がっていると外での暮らしにはもう戻れまいと思うのだ。
そんなある日、かなこが私に「おやつだよ」と何かを差し出した。
なんとなく懐かしい臭いがして、ペロリと舐めてみるとやはり懐かしい味がした。
私はこの味を知っている。
ただ、だいぶ昔だったような……私が考え込んでいると、かなこが話し出した。
「ちびちゃん、覚えてないかな? ちびちゃんが本当に小さい頃にね、これ、1回だけ食べてくれたんだよ。私、ずっとちびちゃんのことが心配で見てたんだ。でも小さい頃は本当に警戒心が強くて、なかなか近付けなくてね。体が小さくて弱ってるみたいだったから、食べてくれたときは本当に嬉しかったな」
ああ、思い出した。
母がいなくなって、ひとりで必死に生きていたあの頃だ。
もうダメかもしれないと思ったときに、誰かの声が聞こえて、それまで経験したことのない何とも言えない幸せな味が口の中に広がったのだ。
その後で何とか持ち直して、野良としてたくましく生きてこられた。
思い出したら涙がこぼれそうになったが、私はそれをぐっと堪えて、かなこに向かって一言「にゃあ」と鳴いてやった。
「そっかー、覚えてるのかー」とかなこは嬉しそうに、私を撫で回す。
吾輩は家猫である。
名前は「ちび」だ。
執筆:妖精社 (ペンネーム)

妖精社(ペンネーム) プロフィール
フリーランスのライター。大学で心理学を専攻し、卒業後には心理カウンセラーとして活動。気付けば副業でやっていたライターが本業に。現在は個人のご相談から企業案件まで幅広く執筆。最近は絵本のシナリオや小説、書籍に関する依頼も急増中。ちんまりとした可愛いもの、もふもふしたものが好きです。