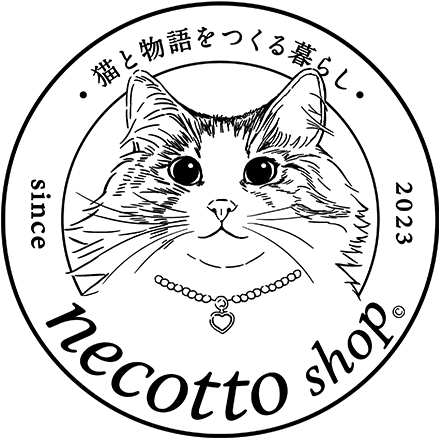創作 2023.09.15 一番星飴商店

「——ごめん、すきな子ができた」
彼の言葉が私の頭の中でぐるぐるとまわる。好きだった茶色の瞳は伏し目がちにゆっくりと閉じられていく。もう、私が大好きなその色をみることはもうないのだと思うと、ほんの少しまた悲しくなった。
ゆらゆらとゆれるオレンジに染まる公園のベンチで私はぼんやりと宙を仰いでいた。
どれくらいの間、そうしていたんだろう。腕時計を彼の部屋に忘れてきてしまったから、時間を確認するすべがない。いや、スマホをみればいいのだけれど、それすらも今は億劫だ。空はすっかり暗くなり、遠くの方でわずかに星がひかる。いちばん星もこの瞳をとおして見つめるとゆらゆらと滲んで揺れてみえる。
「——ごめん、すきな子ができた」罪悪感にとっぷりとつかったその声だけがまた再生される。
ああ、いっそ記憶ごと消してくれたら楽になれるのに。生まれた瞬間から、今までの記憶をぜんぶ消してくれ、神さま。どうか、ああ、どうか。
「——おや、これはこれは、ずいぶんと暗い表情をされていますね」
声がした。穏やかな、夜の中に包まれたような優しい声。
私は涙をごしごしと拭きながら、あたりをきょろきょろと確認してみる。が、あたりには誰もいない。悲しすぎて、ついに幻聴がきこえはじめたか。やばいかもしれない。
「わっ……!?」
ざらりと小さく湿った何かが脚に触れる感触。気がつけば、一匹の白ねこが私の足元にやってきていて、こちらをじっと見つめていたかと思うと、そのふわふわの白い毛を私の黒のパンプスにこすりつけた。彼が誕生日に買ってくれた少し高いパンプス。ヒールが高くて、かわいいけど——でも、本当は、履くと背筋がピンと伸ばされるし、少し窮屈で履いていて居心地が悪かった、なんてこと最後まで彼にはいえなかったな。
「きみ、とっても人懐っこいね……人間がこわくないの?」
私はそう白ねこに声をかけながら、その白い毛をおそるおそる撫でる。首輪もなにもついていないけど、ずいぶんと手入れをされているようだし、飼い猫だろうか。
「ふふ、かわいいね。きみの名前は? きみのご家族は? どこからきたの? なーんて聞いても、教えてくれるわけ、ないか……」
「——はいはい、ワタクシは『シロ』と申します」
「ヒッ……!? しゃ、しゃべった……」
白ねこが私の前でくちをぱくぱくと動かしながら、話をしている。え、これ、本当に喋っている。私、夢を見ているのか。いや、夢に違いない。じゃないと、こんなこと有り得ないもんな。私は白ねこの——いや、シロさんの頰をすりすりと指先で撫でてやる。シロさんはごろごろと喉を鳴らしながら、目を細めた。茶色の瞳、彼の瞳によく似ていてほんの少しだけまた悲しくなる。ああ、ぜんぶ夢だったらいいのに。
「あのう……あなた、お名前は?」
「あ、えっとすみません……名前を聞いておいて……鈴鹿はると申します」
そうシロさんにぺこりと頭を下げると、シロさんは、にいと目を細めて笑って、私の膝に飛び乗る。
「はるさん。良い名前です。私、家はありませんが、『一番星飴商店』を経営しておりますので、よろしければいらっしゃいませんか? きっとはるさんが気にいると思います」
シロさんがそういいながら、私を案内するようにすたすたと夜の道を歩きはじめる。私もベンチから立ち上がると、シロさんのあとをついていく。いつもなら、しゃべる猫のあとなんてついて行ったりしないけど、今日は心が弱っているせいだろうか。
滲んだ一番星をみつめていたせいかもしれない。ついていってもいいかもしれないなんて、思った。
「こちらです」
裏路地を何度か曲がったところに、そのお店はあった。紫のネオンライトで『一番星飴商店』とかかれている。ぼんやりと空を見上げてみると、古びたビルとビル、排水管の隙間から一番星がきらりとひかってみせた。
「さあさあ、はるさん」
「はい、ありがとうございます」
からりとドアベルの音とともにアンティークの家具とカラフルな飴の入った瓶がたくさん視界に入る。赤にピンク、黄色にオレンジ、それから紫、ブルーに、緑色。装飾のほどこされた暖かいライトの光に照らされて、星のようにカラフルにきらきらと光る。シロさんはすたすたと歩くと、その白いふわふわの身体で椅子を押して私に座るように促す。
私はその椅子に座りながら、もう一度その星たちをみつめた。
「まるで、お星さまか、宝石みたいです……とっても綺麗」
「さあ、どれをなめますか?」
「え、舐めてもいいんですか?」
「そりゃあ、飴ですから。舐めなくちゃ意味がないでしょう?」
そういいながら、シロさんはゆるりと瓶のそばに立つと器用に重たそうなガラスの瓶のふたを開ける。からんとガラスのぶつかる音が心地がいい。
「それじゃあ、その綺麗なピンクの……なんの味がするんでしょう?」
「これはペレラという植物ですね。とっても綺麗な色に染まるんです。味も甘酸っぱくてとてもおいしいです」
「ペレラ……聞いたことないや、じゃあそれをいただきたいです」
「もちろん」
シロさんは瓶の中に肉球をつっこむと上手にピンク色の飴をひとつ、取り出して、私に差し出した。ふさふさの白い毛を垂らしながら、私のそばに座ると飴を舐める姿をみつめる。
「あまい……」
甘酸っぱくて、でも柔らかくて優しい味。ふんわりと紫蘇の風味が鼻にひろがって、すっきりしていて、とても食べやすい。
「おいしい……とっても、おいしいです」
「そりゃあ、よかったです。ここの飴はひとつひとつ丁寧につくられているんですよ。あなたのために」
「私の……ために……か」
シロさんはまっすぐに私をみつめる。そのきらきらとした瞳が綺麗で、私は思わずそのねこをぎゅっと抱きしめた。あたたかくて、やさしくて、白くてきらきらとしていて——それから。
気がつけば、涙が溢れていた。かなしいのか、さみしいのか、くるしいのか、ほっとしたのか、気持ちがぐちゃぐちゃしていてわからない。腕の中のシロさんは「にゃあ」とちいさくひと声あげると、そのまま身動き一つせず、おさまってくれていた。
「シロさん……ありがとう、もう一つだけ飴、いいですか」
「もちろん、どれにいたしますか?」
「それじゃあ、この茶色の飴」
シロさんの瞳の色みたいな、彼の瞳の色みたいなそれは薄い茶色でゆらゆらと揺れてひかる。
「それはアールグレイティーですね、どうぞ」
ころりとくちの中に放り込めば、きらきらと紅茶の香りが鼻を抜けていく。さわやかな苦味と甘さ。深く沈んでいた心が浮かび上がっていくような、そんな。涙のせいかほんの少ししょっぱい気もするけれど、それはそれで悪くないと思う。塩のせいで干からびた喉が潤っていくのがわかる。
「ああ、私……もう、大丈夫、だと思う」と泣きながら飴を舐める私をみて、シロさんが笑う。そして、「それは良かったです」と小さくうなずいた。
あれから、どうやって私が帰宅したのか、私は覚えていない。
何度かあのベンチにいってみたけど、シロさんが現れることはなかった。やっぱり夢なのかもしれない。そんなことを考えながら、シャッターが開くことのない『一番星飴商店』にもいってはみる。やはり、今日もシャッターは閉じたまま——。
「あ」
「おや、いらっしゃいませ」
紫のネオンライトが光っていて、扉が開く。あらわれたのは、めがねをかけた初老の男性で、私を見てしずかに微笑んだ。シロさんはいなかった。そううつむいた瞬間、彼の背後から一匹の白いねこが姿を現した。シロさんだった。シロさんはアールグレイの目を細めて小さくのびをすると、「にゃあん」と呑気そうに鳴くのだった。
執筆:張戸侑月

張戸侑月(ハリトユツキ) ペンネーム
大阪府出身。小説家・脚本家・シナリオライター。
主な作品に「夜伽話(yotogi banashi)」、「AM00:00、異星の土地で。」、「good sleep good girl」などがある。