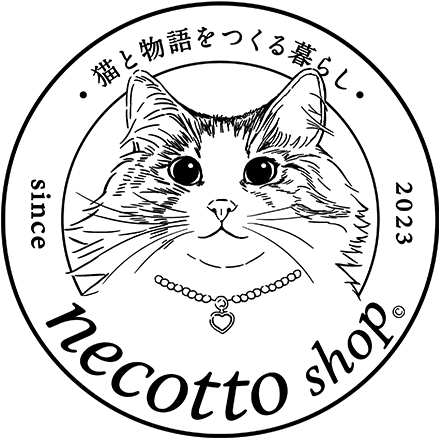主婦 2023.09.20 私は猫が嫌いなのだ。

70歳にもなって動物嫌いを公言すると、偏屈な老婆だと思われるかもしれない。実際、中学生の孫娘には「おばあちゃんって変わり者だよね」と言われるし、趣味の手芸仲間にも「あんなに可愛いのに」と怪訝そうな顔をされる。
でも猫は嫌いだ。
だって我が家に入り込んでくるオス猫は、塀の上を我が物で歩く。さらに丹精込めた家庭菜園を平気で踏み荒らすばかりか、ふらりと現れては庭に断りもなく居座り、たまに焼いた鮭をあげても鳴き声一つ聞かせてくれない。
その傍若無人な態度は、夫によく似ていた。
休みの日に意味もなく家の中をうろつき、私が育てたトマトは色が悪いと文句をつける。ふらりといなくなったかと思えば、行き先は決まってパチンコ屋。夕飯を食べても「おいしかった」の一言すらない。
ついでに夫は関東出身なのに阪神タイガースのファンで、猫はキジトラ模様。ほら、なにからなにまでそっくりでしょう?
夫が二人いるのも、猫が二匹になるのも、どっちもうんざり。
その猫に「トラヤン」という名前をつけたのは夫だった。もちろん愛称があろうとなかろうと猫の態度は変わらずそっけない。でも私が手に乗せた魚は皿に移すまで食べないのに、夫が手に乗せて差し出すと迷わず食べる。あれは納得いかなかったし、すっごく腹立たしかった。だって鮭を焼いたのは私よ?
トラヤンが我が家の庭に現れるようになったのは、東日本大震災が起きた2011年。ナスの収穫前だったから、たぶん8月か9月あたり。夫が定年退職を迎える2年前のことだった。
私の家はサザエさんが住んでいるような木造の平屋で、狭いけれど庭もある。家事の合間に縁側でお茶を飲むのが、私のささやかな楽しみだった。昔からエアコンの冷風が好きになれず、いつも窓を全開にして扇風機はフル稼働。汗だくにはなるけれど、夏ってそういうものだから気にしない。
あの日も私は縁側で、塩を振ったトマトをつまんでいた。家事がひと段落し、夕飯の支度に入るまでの小休止。居間のテレビはつけっぱなしにして、情報番組はいつも音だけを聞いている。
そんな憩いのひと時に、キジトラ模様の猫は唐突に現れた。塀の上からじーっと私に注がれる眼差しは、完全に敵意剥き出し。睨まれているように感じたし、牙を剥いて威嚇もしてきた。勝手に意訳すると「見てんじゃねーよ」って感じね。
その視線がすごく不躾に感じたから、トラヤンの第一印象は最悪。
最初の何日かは塀の上から降りてこなかったけれど、気がつくと庭をうろつくようになっていた。でも出会い以上に最悪だったのは、そこに私の畑があったこと。収穫直前のナス畑を走り回られたあげく、フンを落とされたときには目眩がした。
殺意を込めて竹箒を握ったのは後にも先にも、あの一回だけ。
そのとき私は58歳。当時、頭の中は熟年離婚の計画で埋め尽くされていた。半分は妄想だけれど、半分は本気。あの頃は夫婦喧嘩が絶えなくて、夫と怒鳴り合うのが日常茶飯事になっていた。
肉じゃがの味付けが濃いとか、掃除が行き届いていないとか、どうしてか急に夫の文句が多くなって、もう大変。いまにして思えば、夫も老後の生活に不安を抱いていたのかもしれないけれど、そんなの言ってもらわないとわからないでしょう?
だから向こうも私に嫌気が差しているんだろうなって、そう思うしかなかった。
たぶん二人とも言葉が足りなかったのね。
そんなときに現れた猫だから、私も初めはトラヤンを可愛がろうとした。
きっと癒しがほしかったんだと思う。
猫についても、いろいろと調べてから餌をあげた。味がついている魚はダメだとか、アジの開きやサンマは毒になるとか、知れば知るほど奥が深い。でも少しもなついてくれなかったから、夫だけじゃなく、トラヤンにまでないがしろにされているような気がして、すごく傷ついた。
それから猫と私は、しばらく冷戦状態。感謝もしないくせに、餌をあげるまで庭に居座るトラヤンを憎たらしく思ったこともある。でもいつの間にか、そんな距離感が心地よくなっていた。喉元過ぎれば暑さ忘れるという諺と同じように、ふてぶてしい猫も日常の一部になっていたんでしょうね。
トラヤンがうちに出入りするようになってから2年後の2013年、夫は60歳で定年退職した。ちょうど『高年齢者雇用安定法』が改正された年で、「あと少し遅く生まれていたら、俺も65まで働くはめになっていたんだな」という夫の言葉が印象に残っている。
午前さまの理由は「仕事の付き合い」、喧嘩の決め台詞は「誰が養ってると思ってるんだ」、不満の始まりは「仕事がないから女は楽でいい」と、なにかにつけて仕事仕事ばかり言っていたから、てっきり会社が大好きなんだと思っていた。でも当然ながら夫は夫で、私の知らない苦労をたくさん抱え込んでいたのだろう。わかっていたつもりで、わかっていなかった。
正直、仕事を辞めた夫と四六時中顔を合わせるなんて絶対にうまくいくはずないと思っていたけれど、ありがたいことに予想は大外れ。
トラヤンが、私たちの緩衝材になってくれた。
飼い猫じゃないから、いつ庭に現れるかはわからない。でも夫が「今日は来ねえなあ」とぼやけば、私は「そうね」と返事する。会話は弾まないけれど、猫と同じく夫婦の距離感も、それくらいがちょうどよかった。
一つ、夫には内緒にしているトラヤンの話がある。
買い物帰り、我が家の前で二匹の猫を見かけた。片方はトラヤンで、もう片方は見覚えのないぶち猫だ。うちの塀に登ろうとするぶち猫を、トラヤンが恐ろしい形相で威嚇していた。猫にも縄張り争いがあるのかもしれない。ぶち猫を追い払ったあと、私に見られていると知ったトラヤンはハッと目を見開いた。まさに「見られた!」って顔。思わず笑っちゃった。
この話を夫に明かさなかった理由は一つだけ――普段はクールなトラヤンの名誉を守るために。
定年退職から3年後、夫にがんが見つかった。病気になると、男はとたんに弱くなる。以前は私の手芸品を「女のままごと」ってバカにしていたくせに、今度は「俺にも一つ作ってくれ」なんて言い出して、本当にどうしようもない。私は「棺桶の中に入れるつもり?」なんてひどい冗談を返したけれど、実はすごくつらかった。
私たちはお見合い結婚。昔は独身なんて、親戚どころか近所の人も許してくれない時代だった。義務のように息子を産んで、夫婦円満とは程遠い毎日だったはずなのに……夫がいなくなると思うと、なにも言葉が出てこなくなる。
夫は自宅療養を望んだ。「だってトラヤンは病院に入れないだろう」なんて言っていたけれど、その真意はいまもわからない。がんの告知から一年と経たず、夫は他界した。
それまでもそれからも、トラヤンの気まぐれは変わらない。夫の布団を縁側に敷いていた頃も、葬儀が終えた私が抜け殻になったあとも、キジトラ模様の猫は塀の上からやってくる。餌をねだり、庭を徘徊し、床下の影に寝そべっているかと思えば、いつの間にか消えてしまう。
べつに私を慰めてくれるわけでもないし、なついてくれるわけでもない。ただトラヤンを見ると、私も「生きよう」と思えた。いつか自分の人生に別れを告げる日が来るとしても、それはいまじゃない。老いて、夫を見送り、足腰の痛みもひどくなっているけれど、それでも人生は続いていく。人間などお構いなく、当たり前に生きている猫のように。
そう思えるようになってから、新しいことを始めた。最近、手芸の趣味を活かして、近くのカフェに自作のチャームを置いてもらっている。どれもふてぶてしいキジトラ模様の猫をモチーフにしており、なかなか評判がいい。おかげで半年に一回くらいは、孫にゲームを買ってあげられる。
でも私は猫が嫌いだ。
もう家庭菜園はやめてしまったけれど、フンの恨みはいまも忘れていない。長く姿を見せないと思えば、太った姿で帰ってきたこともある。焼き鮭も皿に移さないと食べてくれないし、本当に憎たらしい。なにより、いないと寂しくなる。お気に入りの縁側に座るたび、あのキジトラ模様を探してしまう自分が悔しくてたまらなかった。会えなくなったら、きっと泣いてしまう。
だから私は猫が嫌いだ。
執筆:町丘澄江

プロフィール
町丘澄江(まちおかすみえ)。
女性。1952年生まれ、東京都出身。五人兄弟姉妹の末っ子。
手芸品『トラヤン』シリーズを近所のカフェに展開中。
好きな曲はオリビア・ニュートン=ジョンの『Take Me Home, Country Roads』。